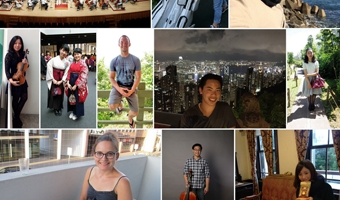【追悼・坂本龍一 Vol.1】第33回定期演奏会 公演レポート
2023年3月28日、音楽家・坂本龍一氏が逝去されました。
PACは2010年4月の第33回定期演奏会にて、氏が作曲された「箏とオーケストラのための協奏曲」を、佐渡裕監督指揮にて世界初演する機会をいただきました。初演の演奏は2011年10月リリースのCD「ryuichi sakamoto presents: sonority of japan 点と面」に収録され、今もお聴きいただけます。
当時、故・平井洋氏が運営されていたウェブサイト「Music Scene」に、音楽評論家の小味渕彦之氏が第33回定期演奏会とCDについての文章を寄稿されていました。残念ながら平井洋氏のウェブサイトは閉鎖されていますが、このたびPACのウェブサイトにて公開させていただくことになりました。Vol.1で公演レポート、Vol.2でCD紹介を掲載しておりますので、ぜひお読みください。
「坂本龍一が箏とオーケストラのためにコンチェルトを書く」ちょうど1年前に発表された、兵庫芸術文化センター管弦楽団(PAC)の年間スケジュールを見たときは驚いたが、箏独奏が沢井一恵だと知って合点がいった。「沢井さんならやりかねない」と思った。ところが沢井と坂本はこれまで面識がなかったという。
沢井一恵のことをあまりご存じない方のために紹介すると、8才より箏曲を宮城道雄に師事し、東京芸術大学卒業後、1979年に夫であった故沢井忠夫と共に沢井箏曲院を設立、古典の演奏とともに邦楽の枠組みを大きく越えた活動を長年に渡って繰り広げてきた。(https://sawaisoukyokuin.com/sawaikazue)例えば1987年に発売された『目と目』というアルバムがある(長らく入手困難な状態にあったが、先だって日本伝統文化振興財団から復刻された。販売はビクターエンタテインメント株式会社)。これは高橋鮎生(現在はAyuoとして活動)のプロデュースで、高橋作品を中心に太田裕美がボーカルで参加するという型破りなものだった。多岐にわたる活動は枚挙にいとまがないが、柴田南雄、高橋悠治、加古隆、クリスチャン・ウルフらの作品を演奏、インドネシアの舞踊家サルドノ・クスモとのコラボレーション、韓国のシャーマン金石出(キム・ソクチュル)達との即興演奏などがある。
今回の新作初演はPACの定期演奏会で、芸術監督の佐渡裕と沢井の共演がグバイドゥーリナ《「樹影にて」~アジアの箏とオーケストラのための》(1998年 NHK交響楽団委嘱作品)の再演を軸に決まり、さらに「是非新作を」ということで坂本に白羽の矢が立った。佐渡は1997年の「PLAYING THE ORCHESTRA 1997 "f"」という坂本のコンサートで指揮をしている。ここで演奏された《Untitled 01》は坂本のソロアルバム『ディスコード』として発売された。それ以前のオーケストラへの取り組みでは1988年に開かれた「Sakamoto Plays Sakamoto」(大友直人指揮 東京交響楽団)もあった。こちらは映画音楽「戦場のメリークリスマス」と「ラストエンペラー」を中心にしたもの。『Playing The Orchestra』としてライブCDが発売されている。その他にいくつかの映画音楽と、オペラ『Life』(1999年)にもオーケストラは使われていた。
坂本、沢井、佐渡の三者で打合せが、オーケストラとの練習が始まる前日(4月5日)に行われた。「(今日は弾かないつもりだったのに)弾くはめになっちゃった」とおどけてみせた沢井が、ソロパートの冒頭を奏でたとたん空気が変わった。スコアに書かれたのは、符頭のみが記された黒玉の音符の上行音形。テンポは指定されず、「very subtly(=繊細に、敏感に)」と指示がある。沢井が施す一音一音への千変万化な表情付けが、静かで雄弁な音楽を生んだ。箏という和楽器を用いた上に、選ばれた音はペンタトニック(五音)音階を基に書かれているから、「日本的」「邦楽的」という形容が出てきてもおかしくはない。ただ坂本は従来から五音音階を効果的に使ってきた。その上で、ミニマル・ミュージックの手法に則ったシークエンスの繰り返しに、独自の繊細な和声で彩った響きの移ろいをトレードマークだとすれば、今回の新作もとりたてて邦楽の世界に寄り添ったわけではない。昨年発売された5年ぶりのアルバム『out of noise』と共通する世界がある。
昨年、坂本のピアノ・ソロ・ツアー"Ryuichi Sakamoto Playing the Piano 2009"を聴いた沢井は「太古の静寂に発光する音を見た」と感じ、「こういう人にこそ箏に関わって欲しい」と確信したそうだ。「(出来上がった譜面は)何の衒いもなく書かれた音符を辿るだけで、古典を弾いている同じ精神に行くことができる、そして古典を超えて美しい」と沢井は今回の練習前に語った。「ぼくは邦楽を全然知らない。知らないだけに新鮮にできた」と坂本は言う。委嘱に当たり坂本は沢井の弾く箏を一時間ほど聴いただけで、沢井は楽器の解説はしていないし、作曲のために楽器の提供も求められなかったという。作曲の構想は昨年秋のヨーロッパツアー中に進められた。
「最近、別に日本の楽器でやる意味があるのかなという音楽を邦楽器でやっている」そうじゃないだろと思って坂本はこの曲を手がけたそうだ。邦楽器の可能性は西洋の音階どおりに音を出すことではなく、そこをはみ出した音程や各々の演奏家独自の味付けにあるというわけだ。自身の最近の活動については「自分では分けてはいないが、(クラシックの)ルーツに帰るじゃないけど、ロックやポップスで育ったのとは違うから」「ポップス的な形態に対する興味はちょっと薄れてきた。でもわからない。次またテクノポップみたいなのやるかもしれない」と語る。「クラシックはミニマリズムで死んだと思ってたけど、演奏も創造行為だということを初めて藤原真理さんのチェロに気づかされた」「ぼくが書いた音符は花の種で、実際に花を咲かせるのは演奏家だと教わった」「ピリオド奏法の可能性もある」と興味深い話も聞くことができた。ペーテル・エトヴェシュ、ジョルジ・クルタークなどをよく聴いているというのも意外なところ。ただし「ブルックナー、マーラーなんて絶対最後まで聴けない」とロマン派が嫌いなのは変わっていないようだ。
作品は続けて演奏される4つの部分から成る。順に「1. still」「2. return」「3. firmament」「4. autumn」と題され、季節が冬から春、夏、秋とめぐってゆく。ステージに並ぶのは4つの箏(すべて十七絃箏)。それぞれに異なった調弦が施されている。オーケストラは2管編成に打楽器、チェレスタとハープを加えた一般的なものだ。
全員が揃った最初の練習(6日)ではオーケストラに明らかな戸惑いも感じられ、まだまだ音楽にはほど遠かった。オーケストラの譜面は完全に五線上に書かれているが、複数名いる弦楽器奏者に「(縦の線を揃えずに)個々のテンポで弾け」「ピッツィカートをばらばらに響かせて」と指示があっても(2. return)、ぴったりと揃ってしまう。管楽器が音を出さずに楽器に息を吹き込み続ける奏法も、現代音楽ではそれほど珍しくないはずなのに、なかなかうまくいかない(1. still)。坂本は3日間リハーサルに立ち会い、会場であるホールに場所を移してからは楽器間のバランスのチェックを入念に行っていた。初日の本番は演奏後に舞台で聴衆の拍手を受けたそうだ。
PACの定期演奏会は金土日曜の3日間開かれ、いずれも午後3時の開演と異例のものだ。第33回(4月9~11日・兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール)となる今回もチケットは売り切れで、坂本作品が演奏されるからというよりは、根強い佐渡裕人気が阪神間の需要にピタリとはまったというところ。11日の3日目を聴いた。この曲には指揮のままに弾くことよりも、自発的な室内楽の流儀が求められるように思う。若いオーケストラも沢井がつま弾く多様な音に触発されて音楽がふわりと浮き上がってきた。「1. still」では管楽器の息の音が自然界の音に聴こえ、「2. return」では響きが微睡んだ。この楽章のソロパートは音形だけが書き込まれ、音高が決められていない。「3. firmament」のミニマル的な手法はおなじみのサカモトサウンド。オーケストラ共々、ソロパートにも細かな動きが多い。ここで箏の絃が切れるというハプニングもあったが、沢井はもろともせずに音楽に没入していた。「4. autumn」では静かに音が沈んで行く。箏の本体を共振させる特殊奏法が多用されて、密やかに震えるノイズが主役となる。もう1曲、沢井が独奏をつとめたグバイドゥーリナ作品が激しいものだけに、坂本作品の極めて静かな響きとの対比が際立った。「ぼくに頼むんだから、普通の現代音楽は期待されてない」と坂本は言うが、ワンフレーズ聴いただけで「坂本龍一」とわかるのと同時に、沢井一恵の「共同」が作品の根幹を貫いている。他にプロコフィエフ《バレエ音楽「ロメオとジュリエット」》の抜粋も演奏された。
小味渕彦之[2010年4月]